\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/
〜ネコポス対応で単品購入の送料が安い商品多数!〜

今回の内容を動画にしました。よろしければそちらもご覧ください。
今回はアクアリウムの頻出課題である
「黒ひげゴケ」
と
「藍藻」
に関するお話です。
彼らはどういう状況で発生するのか、結局どうすればいいのか。
多くのアクアリストがその対策に日々頭を悩ませています。
この記事では黒ひげゴケと藍藻について調べた結果をまとめて、対策としてどうすればいいのかということを私個人の視点で述べました。
結局
「リン酸」
と
「硝酸」
をどうするか。
ここに落ち着きました。
それでは始めていきます。

黒ひげゴケは正式には
「Audouinella sp.」
つまりAudouinella属の一種という扱いです。
これはオージュイネラ属と読み
「紅藻」
の仲間です。
少し調べてみると、次の文献(1)に紅藻の仲間に関する平均湿重量と窒素とリン酸の間には正の相関があることが示されています。
月別のカギイバラノリ平均湿重量と水温,硝酸態窒素濃度およびリン酸態リン濃度の間の相関係数を算出した結果,平均湿重量は水温との間に負の相関が認められ (r=-0.48,P<0.05),逆に,硝酸態窒素濃度 (r=0.54,P< 0.05) とリン酸態リン濃度 (r=0.59,P< 0.05) との間に正の相関が認められた。
(1)参考:田中優平,高瀬智洋,駒澤一朗, 「八丈島沿岸におけるカギイバラノリHypnea japonica(スギノリ日,紅藻)の季節的消長と成熟」,水産増殖 (Aquaculture Sci.) 59 (4), 593 -598 (2011).
黒ひげゴケを培養できればもっと説得力がありますが、それは難しいので今回は分類上仲間であるという点から類推するにとどめます。
つまり同じ紅藻である黒ひげゴケも、窒素やリンが増加した環境では増殖しやすいと考えられます。
よく黒ひげゴケはリン酸の蓄積で発生するとありますが、リン酸だけでなく、硝酸態窒素が多くても発生するようです。
リン酸だけ減らしても窒素が多ければ発生するのかもしれませんね。
リン酸が増えると、窒素が多い環境をさらにブーストして、一気に広がるのかもしれません。
アクアリウムでは硝酸態窒素とリン酸態リンをいかにして減らすかが重要ですね。
結局黒ひげゴケの増殖には窒素とリンが大量にある環境が関係しています。
つまりこれらの栄養分をいかに減らすかという問題になります。
黒ひげゴケを減らすには
このあたりの対応が考えられます。
3については後ほど述べます。市販品を使うのが一番です。
1については、
「十分なカリウムを添加する」
ということが考えられます。
トロピカの茶液は窒素とリンを省いてカリウムと微量元素を主体としている液肥です。これなら窒素とリンが過剰なのにさらに窒素とリンを供給するなんてことがなくて黒髭コケ対策にはいいですね。

結果的に窒素とリンの濃度が減少するので、黒ひげゴケも繁殖用に窒素とリンを利用できなくなって、減少するという理屈です。
2については水換えで窒素とリンを水槽外に排出することで窒素とリンを薄めようということです。
黒ひげゴケ対策にはこのような手段が考えられます。

藍藻は
「シアノバクテリア」
とも呼ばれ、葉緑体の起源と考えれれていて、かなり昔から存在し続けている存在です。
藍藻は酸性環境が苦手です。
このようにラン藻は,幅広い生育環境に適応しているが,なぜか酸性環境は苦手で,pH 4以下の酸性環境から単離される藻類は,ほとんど真核藻類なのである.
参考:仮屋園 遼, 「ラン藻は酸が嫌い」, 生物工学会誌 第99巻 第6号 302.2021.
また次の文献(2)によると、藍藻は窒素が少なく、リンが多いと繁殖するそうです。
ブルームを形成する藍藻類は窒素をめぐる競争に対して優れた競争者であり, 窒素制限下の植物プランクトン群集ではその他の藻類を排除し, 優占できることが知られている。
(2)参考:本間隆満 朴虎東, 「諏訪湖におけるMicrocystis種組成および藍藻毒素microcystin濃度に及ぼす硝酸態窒素・リン酸態リン濃度の影響」, 水環境学会誌 2005 年 28 巻 6 号 p. 373-378.
そして水生植物に関して調査した文献(3)によると、ある水性植物が吸収する窒素・リンの比は次のようになります。
吸収されたTINおよびPO4-Pの比は、生育時期によって変化したが、3.8~6.8の間にあることが明らかになった。
(3)参考:小浜暁子、江成敬次郎、玉置智、中山正与, 「水生植物(マコモ)による窒素・リン吸収量の評価」, 日本水処理生物学会誌 第39巻 第2号 59-66 (2003).
これを参考にすると、水草は最低でもリンの約4倍窒素を吸収するということです。
するとアクアリウムでは水草が成長する間、窒素を多く消費し、リンが余ります。
魚粉の構成比は
「N:P:K(窒素/リン/カリ) 5〜9:5〜15:0」
くらいです。
水槽に添加されるリンのほうが窒素より多いんです。
つまりものすごくリンは余ります。
すると藍藻は窒素が少なくてリンが多い環境で優位に立つので、よく繁殖するということになります。
水槽では硝化の影響でpHが下がるので、そこがかろうじて藍藻を抑えている要素で、それでもリン酸過剰になるとさすがに繁殖を始めるといったところでしょうか。
上の文献ではpHは4以下での話でした。
我が家の水槽のpHは6くらいなので、藍藻は繁殖できるのかもしれませんね。
ちなみに硝化とpHについては以下でまとめています。
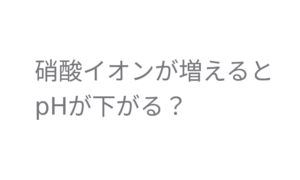
上で述べたように藍藻を減少させるには
この二つが重要です。
実際の対策としては
くらいです。
1はリン酸を薄めるという発想です。
ただやりすぎるとpHが酸性から中性に傾く、つまりpHが上がるので、藍藻に有利な環境になります。
まあこなれた水槽は多少水換えしたくらいではpHがものすごく上がるということはないでしょうから、あまり気にしなくてもよいかもしれません。
海水魚水槽では気をつけないといけないでしょうけど。
2はリン酸を物理的に除去するという発想です。
これについては後述します。市販の除去剤を使いましょう。
3は物量で攻めて、水草にリン酸を消費してもらうという発想です。
黒ひげゴケのところで述べたように、カリウムが不足しがちなので、カリウムの添加をすると効果的かもしれません。

藍藻の対策はこんな感じになります。
ヒメタニシなどの貝類は濾過摂食という能力を持っており、藍藻を食べることが可能です。
3)水質浄化を目的として大型二枚貝を用いて植物プランクトンを除去する場合,擬糞となったラン藻類が再懸濁することがないよう,擬糞を回収する必要がある。
西尾 孝之, 大島 詔, 北野 雅昭, 二枚貝を用いたアオコの繁殖した都市公園池の水質改善の試みにおける擬糞回収の有効性評価,日本水処理生物学会誌/50 巻 (2014) 1 号

ヒメタニシは濾過摂食の能力を持っているので藍藻を食べる可能性が高いです。実際入れると緑色に染まった水槽が透明になっていきます。
ただ上の文献のように、食べられた藍藻は死滅しないので、糞を取り除く必要があります。
ただ、水槽という小さな空間では散らばって繁殖している藍藻を糞として排出して、人間が集めて回収しやすくするという効果はあるので、藍藻が結構あるときはヒメタニシを入れてみるといいかもしれません。
もちろん糞は見つけ次第スポイトなどで回収します。
リン酸を除去できる薬品も販売されています。
色々ありますが、お好みで選んでください。
ただ、試薬系は魚への影響がゼロではないときが多いので成体の状態をよく観察して慎重に導入してください。
今回は黒ひげゴケと藍藻について述べました。
対策としては
このようになります。
難しいなら水槽リセットです。